問題演習


問題一覧
【一問一答】8.3.2 神経系 – 下行性伝導路:錐体路 (皮質脊髄路)
【錐体路 (皮質脊髄路)】
大脳皮質の運動野から始まり、脊髄前角まで至る随意運動の伝導路は、延髄の錐体と呼ばれる盛り上がりをつくって下行することから ( 路) という
後索路
錐体路
錐体外路
(解答) 錐体路
大脳皮質の運動野から始まり、脊髄前角まで至る随意運動の伝導路を錐体路といいます。
錐体路は別名、 ( 路) という
脊髄視床路
皮質脊髄路
(解答) 皮質脊髄路
錐体路は別名、皮質脊髄路といいます。
伝導路の命名法は基本的に「起始 → 停止」です。皮質脊髄路は大脳皮質 → 脊髄へ至る路という意味です。
錐体路は ( 回) に存在する巨大錐体細胞から起こる
中心前回
中心後回
(解答) 中心前回
錐体路は中心前回に存在する巨大錐体細胞から始まります。
錐体路 (皮質脊髄路) のニューロンは中心前回から脊髄前角までひとつのニューロンが下行します。よって中枢神経内で最も長いニューロンであると言えます。(感覚性の伝導路である脊髄視床路や後索内側毛帯路は中心後回に到達するまでに2度ニューロンの乗り換えがある)
錐体路にて、中心前回の巨大錐体細胞から起こった軸索は、視床とレンズ核の間を通る ( ) を下行し脳幹へと至る
内包
脳梁
弓状線維
(解答) 内包
中心前回の巨大錐体細胞から起こった軸索は内包を下行し、脳幹へと至ります。
錐体路は中脳では ( ) を下行する
大脳脚
中脳被蓋
中脳蓋
(解答) 大脳脚
錐体路は中脳では大脳脚を下行します。
錐体路は橋では ( ) を下行する
橋底部
橋被蓋
(解答) 橋底部
錐体路は橋では橋底部を下行します。
錐体路の名前の由来となっている延髄の錐体は、延髄の ( 側) にみられる逆三角形の盛り上がりである
腹側
背側
(解答) 腹側
錐体路の名前の由来となっている延髄の錐体は、延髄の腹側にみられる逆三角形の盛り上がりをいいます。
錐体路の線維のうち、約 ( %) の線維は延髄下端の錐体交叉で交叉し反対側に入る
20%
80%
(解答) 80%
錐体路の線維のうち、約80%の線維は延髄下端の錐体交叉で交叉し反対側に入ります。
錐体路にて、延髄下端の錐体交叉で交叉した線維は、脊髄の ( 索) を下行する
前索
側索
後索
(解答) 側索
錐体路にて、延髄下端の錐体交叉で交叉した線維は脊髄の側索を下行します。
延髄下端の錐体交叉で交叉し、側索を下行する錐体路の別名を ( 皮質脊髄路) という
前皮質脊髄路
外側皮質脊髄路
(解答) 外側皮質脊髄路
延髄下端の錐体交叉で交叉し、側索を下行する錐体路の別名を外側皮質脊髄路といいます。
錐体路にて、延髄下端で交叉しなかった線維は、脊髄の ( 索) を下行し、前角細胞に入る高さで交叉する
前索
側索
後索
(解答) 前索
錐体路にて、延髄下端で交叉しなかった線維は、脊髄の前索を下行し、前角細胞に入る高さで交叉します。
結果的に、全ての錐体路は反対側の前角細胞に終わることになります。
延髄下端の錐体交叉で交叉せず、前索を下行する錐体路の別名を ( 皮質脊髄路) という
前皮質脊髄路
外側皮質脊髄路
(解答) 前皮質脊髄路
延髄下端の錐体交叉で交叉せず、前索を下行する錐体路の別名を前皮質脊髄路といいます。
錐体路の障害 (上位運動ニューロン障害) により上肢は屈筋、下肢は伸筋の筋緊張が高まる ( 麻痺) が生じる
痙性麻痺
弛緩性麻痺
(解答) 痙性麻痺
錐体路の障害により上肢は屈筋、下肢は伸筋の筋緊張が高まる痙性麻痺が生じます。
脳卒中のような上位運動ニューロンの障害では、一般に痙性麻痺が起こります。屈筋もしくは伸筋のどちらかの緊張が亢進するのが特徴で、上肢は屈筋、下肢は伸筋の緊張が高まる結果、マン-ウェルニッケ拘縮という肢位となります。また、腱反射の充進やバビンスキー反射などの病的反射が出現します。
脊髄の前角細胞や末梢神経などの下位ニューロンが障害された場合 ( 麻痺) が生じる
痙性麻痺
弛緩性麻痺
(解答) 弛緩性麻痺
脊髄の前角細胞や末梢神経などの下位ニューロンが障害された場合、弛緩性麻痺が起こり、筋緊張が失われ萎縮が起こります。
弛緩性麻痺の特徴として、麻痺を起こしている筋肉が細かくピクピクと動く筋線維束攣縮がみられます。
錐体路以外の下行性伝導路を総称して錐体外路という
○
×
(解答) ○
錐体路以外の下行性伝導路を総称して錐体外路といいます。
かつては錐体路=随意運動、錐体外路=不随意運動という概念が存在しましたが、錐体路と錐体外路は協調して働き、大脳基底核を経由する運動性出力も錐体路を主要な出力とすることから、錐体外路=不随意運動を司るというのは間違いです。ですが、大脳基底核が障害を受けたときに、基底核変性疾患としてさまざまな不随意運動が出現するので、疾患分類として錐体外路疾患という名称が使われています。
おまけのゴロ:好いた色(錐体路)
中心全開、内股、大開脚、身体交叉し、即サック
中心前回 → 内包 → 大脳脚 → 錐体交叉 → 側索
次の問題
[clink url=”https://www.anatomy.tokyo/oqoa/【一問一答】8-3-3-1-神経系-上行性伝導路-1-脊髄視床路/”]
[clink url=”https://www.anatomy.tokyo/oqoa/【一問一答】目次/”]
- 【一問一答】8. 神経系
- 8.1.1 神経系概論
- 8.2.1 中枢神経系 – 脊髄
- 8.2.2 中枢神経系 – 延髄と橋
- 8.2.3 中枢神経系 – 中脳
- 8.2.4 中枢神経系 – 小脳
- 8.2.5 中枢神経系 – 間脳
- 8.2.6.1 中枢神経系 – 大脳皮質
- 8.2.6.2 中枢神経系 – 大脳基底核・大脳白質
- 8.2.7 神経系 – 脳室系・髄膜・脳脊髄液
- 8.3.2 神経系 – 下行性伝導路:錐体路 (皮質脊髄路)
- 8.3.3.1 神経系 – 上行性伝導路 (1) 脊髄視床路
- 8.3.3.2 神経系 – 上行性伝導路 (2) 後索-内側毛帯路
- 8.3.3.3 神経系 – 上行性伝導路 (3) 脊髄小脳路
- 8.3.3.4 神経系 – 上行性伝導路 (4) 視覚伝導路
- 8.3.3.5 神経系 – 上行性伝導路 (5) 聴覚伝導路、平衡覚伝導路
- 8.3.3.6 神経系 – 上行性伝導路 (6) 味覚と嗅覚の伝導路
- 8.4.1.1 神経系 – 末梢神経系 脳神経 I 嗅神経
- 8.4.1.2 神経系 – 末梢神経系 脳神経 II 視神経
- 8.4.1.3 神経系 – 末梢神経系 脳神経 III 動眼神経
- 8.4.1.4 神経系 – 末梢神経系 脳神経 IV 滑車神経
- 8.4.1.5 神経系 – 末梢神経系 脳神経 V 三叉神経
- 8.4.1.6 神経系 – 末梢神経系 脳神経 VI 外転神経
- 8.4.1.7 神経系 – 末梢神経系 脳神経 VII 顔面神経
- 8.4.1.8 神経系 – 末梢神経系 脳神経 VIII 内耳神経
- 8.4.1.9 神経系 – 末梢神経系 脳神経 IX 舌咽神経
- 8.4.1.10 神経系 – 末梢神経系 脳神経 X 迷走神経
- 8.4.1.11 神経系 – 末梢神経系 脳神経 XI 副神経
- 8.4.1.12 神経系 – 末梢神経系 脳神経 XII 舌下神経
[dfads params=’groups=1121&limit=1&orderby=random’]
[dfads params=’groups=1124&limit=1&orderby=random’]



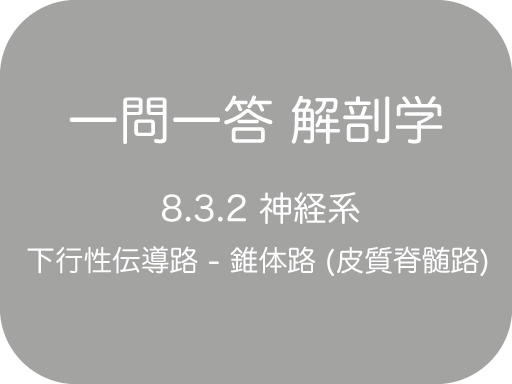
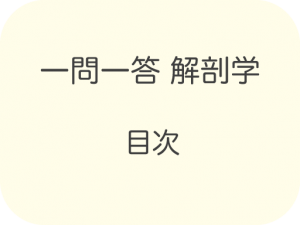
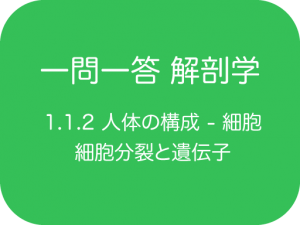
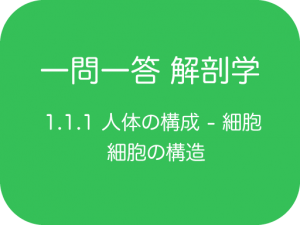
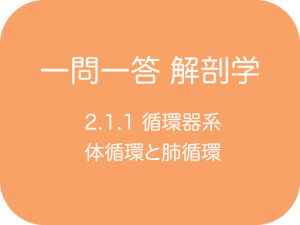




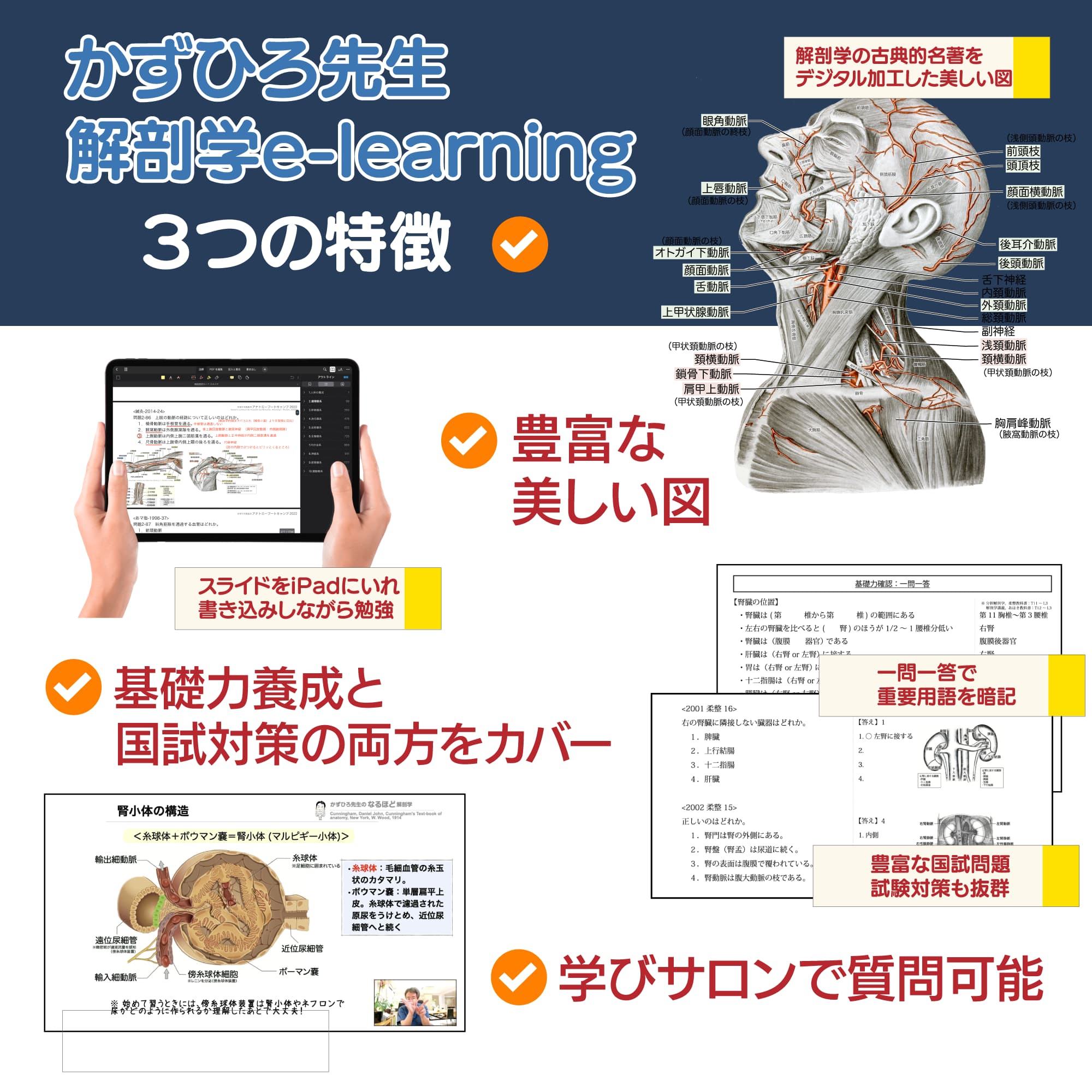
コメント