問題演習


問題一覧
【一問一答】8.2.7 神経系 – 脳室系・髄膜・脳脊髄液
【脳室系】
( 脳室) は対をなす
側脳室
第三脳室
第四脳室
(解答) 側脳室
側脳室は対をなします。
対をなす側脳室を1,2と数えて、第三脳室、第四脳室となります。
間脳に挟まれた正中部に ( 脳室) が存在する
側脳室
第三脳室
第四脳室
(解答) 第三脳室
間脳に挟まれた正中部に第三脳室が存在します。
第三脳室の後上壁より ( ) が突出する
松果体
下垂体
(解答) 松果体
第三脳室の後上壁より松果体が突出します。
脳室系とは関係ないですが、松果体の位置を聞かれたときに2つの言い方があります。ひとつは、「第三脳室の後上壁より後方に突出する」。もうひとつは「間脳の背側」。
第三脳室は間脳の正中部にあるので、第三脳室の後上壁から突出する松果体も間脳の一部であることがわかります。
延髄・橋と小脳に囲まれたところに ( 脳室) が存在する
側脳室
第三脳室
第四脳室
(解答) 第四脳室
延髄・橋と小脳に囲まれたところに第四脳室が存在します。
小脳を脳幹から切り離すと、第四脳室底は ( ) となって見える
ダグラス窩
菱形窩
中心窩
(解答) 菱形窩
小脳を脳幹から切り離すと、第四脳室底は菱形窩となって見えます。
側脳室と第三脳室は ( ) で連絡する
室間孔
中脳水道
正中口
外側口
(解答) 室間孔
側脳室と第三脳室は室間孔で連絡します。
第三脳室と第四脳室は ( ) で連絡する
室間孔
中脳水道
正中口
外側口
(解答) 中脳水道
第三脳室と第四脳室は中脳水道で連絡します。
第四脳室は脊髄の ( ) に移行する
前正中裂
後正中溝
中心管
(解答) 中心管
第四脳室は脊髄の中心管に移行します。脊髄中心管は脳室ではないですが、脳室に隣接することから、機能的に脳室系に含められると考えられます。
各脳室にある ( ) より脳脊髄液が分泌される
脈絡膜
脈絡叢
クモ膜顆粒
(解答) 脈絡叢
各脳室にある脈絡叢より脳脊髄液が分泌されます。
脈絡膜:眼球壁の中層をしめる眼球血管膜。強膜を裏打ちする。
クモ膜顆粒:クモ膜が上矢状静脈洞の内部に突出したもの。脳脊髄液が静脈に吸収される部位。
【広辞苑より】
みゃく‐らく【脈絡】
*血の流れる脈管。
*物事のつながり。すじみち。「—のない話」
脳室を満たした脳脊髄液は ( 脳室) よりクモ膜下腔に出る
側脳室
第三脳室
第四脳室
(解答) 第四脳室
脳室を満たした脳脊髄液は第四脳室よりクモ膜下腔に出ます。
第四脳室よりクモ膜下腔へ通じる出口は ( ヶ所) ある
2ヶ所
3ヶ所
4ヶ所
(解答) 3ヶ所
第四脳室よりクモ膜下腔へ通じる出口は3ヶ所あります。
正中口:第四脳室背面の正中部に一つ(マジャンディー孔)
外側口:左右に1対 (ルシュカ孔)
※ 正中口、外側口が「口」なのに対し、マジャンディー孔、ルシュカ孔は「孔」
脳室の内面は ( 細胞) に覆われる
星状膠細胞
希突起膠細胞
小膠細胞
上衣細胞
(解答) 上衣細胞
脳室の内面は上衣細胞という神経膠細胞でできた単層立方上皮に覆われます。
【髄膜】
髄膜は ( ・ ・ ) の3枚の膜よりできる
強膜・脈絡膜・網膜
硬膜・クモ膜・軟膜
(解答) 硬膜・クモ膜・軟膜
髄膜は硬膜・クモ膜・軟膜の3枚の膜よりできます。
髄膜のうち、 ( ) は骨膜の役割もある
硬膜
クモ膜
軟膜
(解答) 硬膜
硬膜には骨膜の役割もあります。硬膜は内外2葉よりなり、外葉は骨膜に相当し、頭蓋骨や脊柱管の内面に密着します。
脳硬膜の外葉と内葉は大部分の部位で癒合しているが、一部では両葉が開いており、そこに静脈血が流れる ( ) を形成する
冠状静脈洞
硬膜静脈洞
強膜静脈洞
(解答) 硬膜静脈洞
脳硬膜の外葉と内葉は大部分の部位で癒合しているが、一部 (大脳鎌や小脳テントの縁)では両葉が開いており、そこに静脈血が流れる硬膜静脈洞を形成します。
硬膜が合わさり大脳縦裂に入り込み、 ( ) となって左右の大脳半球を仕切る
大脳鎌
小脳テント
(解答) 大脳鎌
硬膜が合わさり大脳縦裂に入り込み、大脳鎌となって左右の大脳半球を仕切ります。
硬膜が合わさり大脳と小脳の間で水平方向に延びたものを ( ) といい、大脳と小脳を仕切る
大脳鎌
小脳鎌
小脳テント
(解答) 小脳テント
硬膜が合わさり大脳と小脳の間で水平方向に延びたものを小脳テントといい、大脳と小脳を仕切ります。
※ 大脳半球と小脳の間の陥凹は小脳横裂といいます。大脳横裂は大脳と視床の間の陥凹をさします。
( )は硬膜の内面に接し、脳の表面を覆う軟膜との間に細い糸状の結合組織の線維を張り巡らしている。
クモ膜
脈絡膜
(解答) クモ膜
クモ膜は硬膜の内面に接し、脳の表面を覆う軟膜との間に細い糸状の結合組織の線維を張り巡らしています。
硬膜とクモ膜の間は ( ) というリンパ間隙が存在する。
硬膜下腔
クモ膜下腔
(解答) 硬膜下腔
硬膜とクモ膜の間は硬膜下腔といいます。一種のリンパ間隙と考えられます。
標準組織学では、硬膜下腔は上下面とも中皮で覆われ一種の通液路としてリンパ液が流れていると記述がありますが、生体では通常ほとんど隙間がないという報告があります。
硬膜とクモ膜の結合は緩いので、架橋静脈の破損などによる硬膜下血腫などで病的に拡大することがあります。
Yamashima, T., & Friede, R. L. (1984). Light and Electron Microscopic Studies on the Subdural Space, the Subarachnoid Space and the Arachnoid Membrane. Neurologia medico-chirurgica, 24(10), 737-746. doi:10.2176/nmc.24.737
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nmc1959/24/10/24_10_737/_article
クモ膜と軟膜の間を ( ) といい、脳脊髄液で満たされる
硬膜下腔
クモ膜下腔
(解答) クモ膜下腔
クモ膜と軟膜の間をクモ膜下腔といい、脳脊髄液で満たされます。
クモ膜には血管が分布する
○
×
(解答) ×
クモ膜には血管は分布していません。
ウイリス動脈輪を始めとする、大脳に分布する血管はクモ膜下腔を走行していますが、クモ膜自体には血管は分布していません。
脳および脊髄の表面に密着する膜を ( ) という
硬膜
クモ膜
軟膜
(解答) 軟膜
脳および脊髄の表面に密着する膜を軟膜といいます。脳や脊髄の切れ込みや溝に沿い、すみずみまで入り込んでいます。
【脳脊髄液】
脳脊髄液は各脳室の (A. ) から分泌され、第四脳室の正中口と外側口よりクモ膜下腔に出て、 (B. ) より硬膜静脈洞に吸収される
A. クモ膜顆粒 B. 脈絡叢
A. 脈絡叢 B. クモ膜顆粒
(解答) A. 脈絡叢 B. クモ膜顆粒
脳脊髄液は各脳室の脈絡叢から分泌され、第四脳室の正中口と外側口よりクモ膜下腔に出て、クモ膜顆粒より硬膜静脈洞に吸収されます。
次の問題
[clink url=”https://www.anatomy.tokyo/oqoa/【一問一答】8-3-2-神経系-下行性伝導路:錐体路/”]
[clink url=”https://www.anatomy.tokyo/oqoa/【一問一答】目次/”]
- 【一問一答】8. 神経系
- 8.1.1 神経系概論
- 8.2.1 中枢神経系 – 脊髄
- 8.2.2 中枢神経系 – 延髄と橋
- 8.2.3 中枢神経系 – 中脳
- 8.2.4 中枢神経系 – 小脳
- 8.2.5 中枢神経系 – 間脳
- 8.2.6.1 中枢神経系 – 大脳皮質
- 8.2.6.2 中枢神経系 – 大脳基底核・大脳白質
- 8.2.7 神経系 – 脳室系・髄膜・脳脊髄液
- 8.3.2 神経系 – 下行性伝導路:錐体路 (皮質脊髄路)
- 8.3.3.1 神経系 – 上行性伝導路 (1) 脊髄視床路
- 8.3.3.2 神経系 – 上行性伝導路 (2) 後索-内側毛帯路
- 8.3.3.3 神経系 – 上行性伝導路 (3) 脊髄小脳路
- 8.3.3.4 神経系 – 上行性伝導路 (4) 視覚伝導路
- 8.3.3.5 神経系 – 上行性伝導路 (5) 聴覚伝導路、平衡覚伝導路
- 8.3.3.6 神経系 – 上行性伝導路 (6) 味覚と嗅覚の伝導路
- 8.4.1.1 神経系 – 末梢神経系 脳神経 I 嗅神経
- 8.4.1.2 神経系 – 末梢神経系 脳神経 II 視神経
- 8.4.1.3 神経系 – 末梢神経系 脳神経 III 動眼神経
- 8.4.1.4 神経系 – 末梢神経系 脳神経 IV 滑車神経
- 8.4.1.5 神経系 – 末梢神経系 脳神経 V 三叉神経
- 8.4.1.6 神経系 – 末梢神経系 脳神経 VI 外転神経
- 8.4.1.7 神経系 – 末梢神経系 脳神経 VII 顔面神経
- 8.4.1.8 神経系 – 末梢神経系 脳神経 VIII 内耳神経
- 8.4.1.9 神経系 – 末梢神経系 脳神経 IX 舌咽神経
- 8.4.1.10 神経系 – 末梢神経系 脳神経 X 迷走神経
- 8.4.1.11 神経系 – 末梢神経系 脳神経 XI 副神経
- 8.4.1.12 神経系 – 末梢神経系 脳神経 XII 舌下神経
[dfads params=’groups=1121&limit=1&orderby=random’]
[dfads params=’groups=1124&limit=1&orderby=random’]



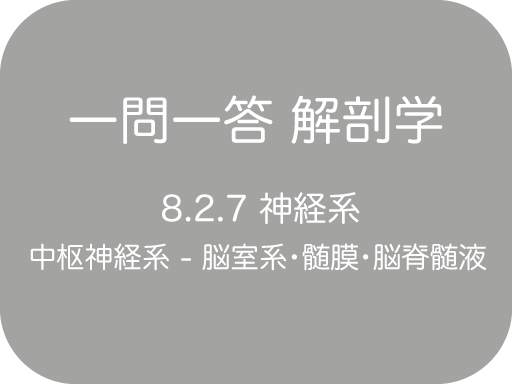
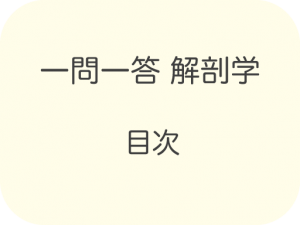
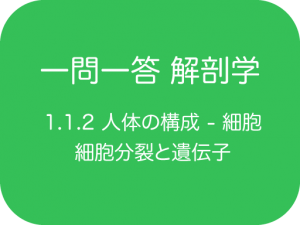
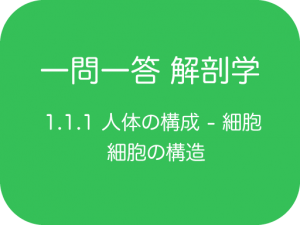
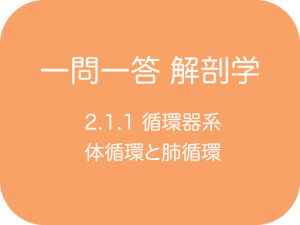




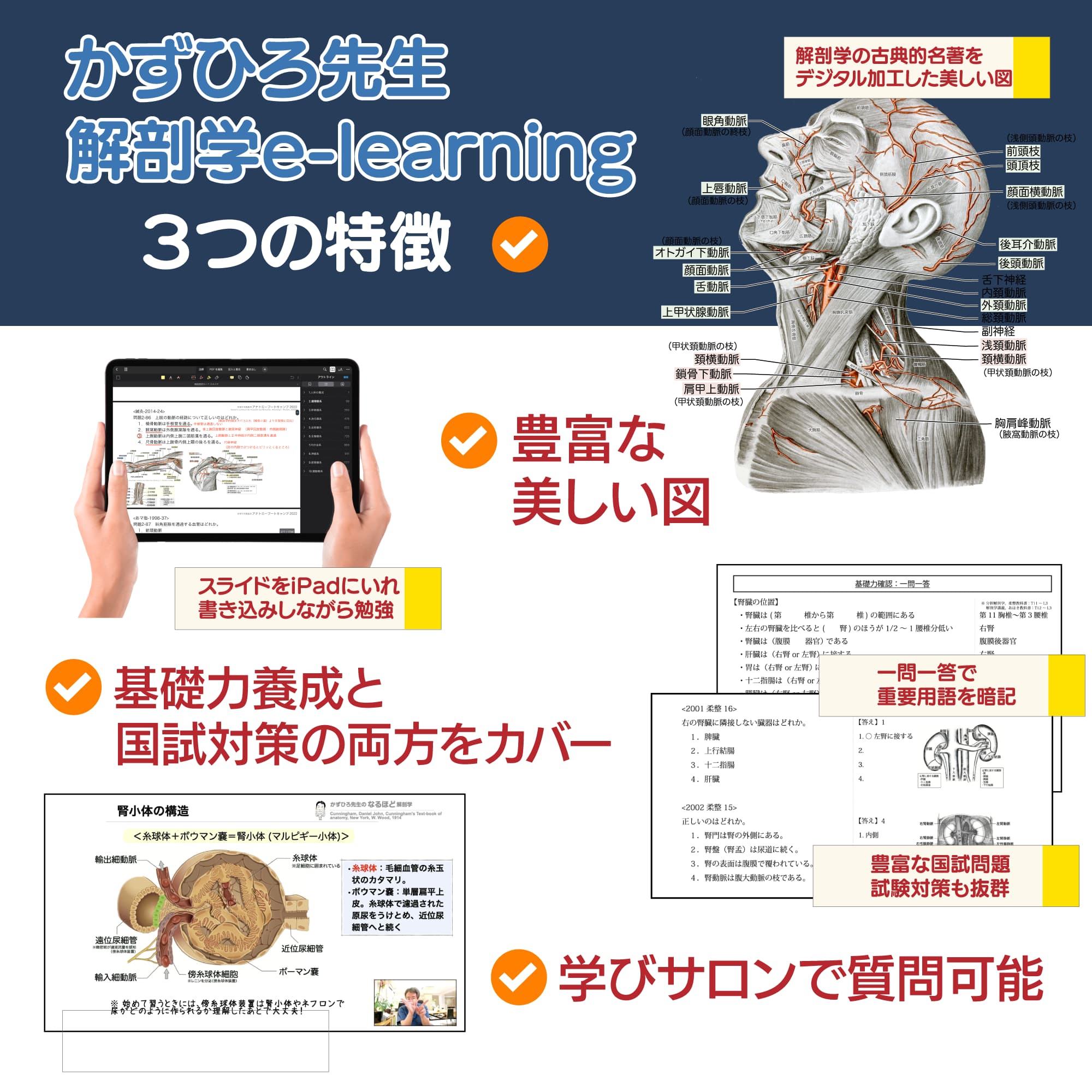
コメント